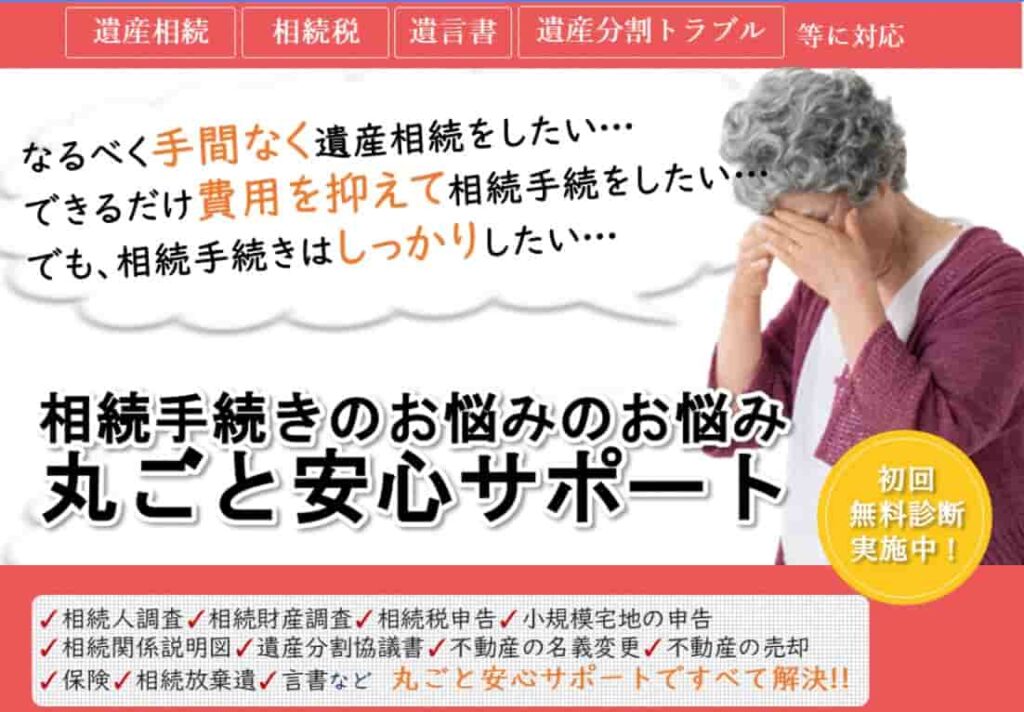ご心労お察しいたします。相続は、故人を偲ぶ大切な時期であると同時に、残念ながらご家族の間でトラブルが起こりやすいタイミングでもあります。
「うちは家族仲が良いから大丈夫」「財産なんてほとんどないから揉めようがない」…そう思っていても、実際に相続が発生すると、お金の問題が絡むことで、それまで良好だった関係に思わぬ亀裂が入ってしまうことは、決して珍しい話ではありません。秋田のような地域でも、相続トラブルのご相談は後を絶ちません。
相続税がかかるのは東京だと6人に1人、全国平均でも約10人に1人(関連記事:相続税はいくらまで無税?いくらからかかる?秋田市の税理士が解説)ですが、相続手続きそのものは、亡くなった方がいれば全てのご家庭で発生する問題です。
この記事では、相続に関する実務経験豊富なあきた相続・贈与相談プラザ(運営:秋田税理士事務所)の専門家(税理士・司法書士)が、実際に見てきた事例をもとに、相続で揉めてしまうご家族の特徴と、そうならないための対策について、詳しく解説します。
この記事のポイント
- 相続トラブルは特別な家庭だけの問題ではなく、誰にでも起こりうる。
- 揉める家族には共通の特徴がある(遺言書の問題、介護負担、手続きの丸投げなど)。
- トラブルを避ける鍵は「有効な遺言書」と「生前のコミュニケーション」。
- 自筆の遺言書はリスクが高い!専門家が関与する「公正証書遺言」が確実。
- 相続手続きは複雑で負担大。専門家への依頼でスムーズな解決とトラブル防止を。
もし、少しでもご自身の状況に当てはまる点があれば、それはトラブルのサインかもしれません。手遅れになる前に、ぜひ私たち専門家にお話しをお聞かせください。
\初回無料診断/
要注意!相続で揉める家族の5つの特徴
私たちがこれまでのご相談や実務で見てきた中で、相続トラブルに発展しやすいご家庭には、いくつかの共通した特徴が見られます。あなたの場合はどうでしょうか?
- 「秘密の遺言書」が存在する(または、存在が疑われる)
- そもそも法的に有効な遺言書がない
- 遺言書はあるが、なぜその内容なのか「気持ち」が伝わっていない
- 特定の相続人だけが、長年親の介護を負担していた
- 面倒な相続手続きを、特定の相続人に丸投げしている
特徴1:「秘密の遺言書」が存在する(または、存在が疑われる)
「お父さんが遺言書を書いてタンスにしまっていたらしい」「お母さんがエンディングノートに何か書いていたみたいだけど、内容は知らない」…
このように、遺言書やそれに類するものを本人がこっそり作成し、家族に内容を秘密にしているケースは非常に危険です。
なぜなら、相続が始まった後、最初にその遺言書を見つけた相続人が、もし自分に不利な内容だと感じたらどうするでしょうか? 良心的な方ばかりとは限りません。破り捨てられたり、隠されたりしてしまう可能性がゼロではないのです。(遺言書の破棄や隠匿は法的に罰せられますが、誰も気づかなければ立証は困難です)。
また、後から「実はこんな遺言書があった」と出てきた場合、「本当に本人が書いたのか?」「誰かに無理やり書かされたのでは?」といった疑念が生じ、かえって争いの火種になることもあります。
特徴2:そもそも法的に有効な遺言書がない
これが最も多いトラブルの原因かもしれません。遺言書が全くない場合、法律で定められた相続人全員で「遺産分割協議」を行い、誰がどの財産を相続するかを決めなければなりません。
しかし、相続人それぞれの希望や言い分が対立し、話し合いがまとまらないケースが非常に多いのです。「長男だから家を継ぐべきだ」「いや、平等に分けるべきだ」「生前にお金をもらっていたはずだ」など、収拾がつかなくなることも少なくありません。
また、「遺言書を書いたつもり」でも、それが法的な要件を満たしておらず無効になってしまうケースも後を絶ちません。特に、ご自身だけで作成する「自筆証書遺言」は、日付の書き方、押印の種類、訂正方法など、細かいルールがたくさんあり、一つでも間違えると無効になるリスクが高いのです。
特徴3:遺言書はあるが、なぜその内容なのか「気持ち」が伝わっていない
たとえ法的に有効な遺言書があり、その存在を家族が知っていたとしても、それだけでは不十分な場合があります。
例えば、「長男には家を、次男には預金を全て」という遺言があったとします。その分け方になった理由、例えば「長男には家業を継いでほしいから」「次男にはこれまで苦労をかけたから」といった故人の想いや背景が、遺言書だけでは伝わりにくいことがあります。
理由が分からないまま一方的な内容の遺言書だけが残されると、「なぜ自分だけ少ないんだ」「不公平だ」といった不満や疑念が相続人に生まれ、感情的な対立に発展してしまう可能性があります。遺言書の内容だけでなく、その背後にある「気持ち」を伝えることが、円満な相続には不可欠なのです。
特徴4:特定の相続人だけが、長年親の介護を負担していた
「お母さんの介護、ほとんど私一人でやったのに…」「兄さんは遠くにいて何もしなかったくせに…」
このように、特定の相続人が、亡くなった方の生前の療養看護や財産の維持管理に特別な貢献(寄与)をしていた場合も、トラブルになりやすい典型的なパターンです。
介護を一身に担ってきた相続人は、「その分、遺産を多くもらうのが当然だ」と考えがちです。法律上も「寄与分」として、貢献度に応じて相続分を増やすことが認められる場合がありますが、その貢献度を客観的に証明し、他の相続人全員に納得してもらうのは非常に困難です。介護にかかった費用や労力を金銭に換算するのは難しく、感情的な対立も生まれやすいため、寄与分を巡る争いは長期化しやすい傾向があります。
生前に、介護の負担について家族間で話し合い、その貢献に報いる方法(例えば遺言書で明確にするなど)を決めておくことが望ましいでしょう。
特徴5:面倒な相続手続きを、特定の相続人に丸投げしている
相続が発生すると、預貯金の解約・名義変更、不動産の相続登記、株式の移管、相続税の申告(必要な場合)など、非常に多くの煩雑な手続きが必要になります。
これらの手続きは、戸籍謄本などの必要書類を集めたり、銀行や役所、法務局などに何度も足を運んだりする必要があり、時間も手間もかかります。特に、役所や金融機関は平日の昼間しか開いていないため、仕事をしている方にとっては大きな負担です。
「長男(あるいは、近くに住んでいる人)が全部やってくれるだろう」と、手続きの負担を特定の相続人に押し付けてしまうと、その相続人には不満が溜まります。「なんで自分だけこんな大変な思いを…」と感じ、他の相続人との間で不公平感が生じ、関係が悪化する原因になります。
また、手続きを進める中で、他の相続人に不信感を抱かれるようなことがあれば、さらなるトラブルに発展しかねません。
相続手続きは、相続人全員で協力して進めるか、難しい場合は私たちあきた相続・贈与相談プラザのような専門家に遺産整理業務としてまとめて依頼するのが、最もスムーズで公平な方法と言えます。私たちは、戸籍収集から財産調査、遺産分割協議書の作成サポート、各金融機関での手続き、不動産の名義変更(司法書士連携)、相続税申告(税理士)まで、ワンストップで代行することが可能です。
【実話から学ぶ】相続トラブル事例 ~ あなたの家族は大丈夫? ~
ここでは、実際にあった、あるいは起こりうる相続トラブルの事例をいくつかご紹介します。決して他人事と思わず、ご自身の状況と照らし合わせてみてください。「うちは大丈夫」と思っていても、ちょっとしたボタンの掛け違いで、深刻な事態に発展してしまう可能性があるのです。
事例1:良かれと思って書いた自筆遺言書が無効に…
Aさん(70代女性)は、ご主人が亡くなった後、2人の息子さん(長男Bさん、次男Cさん)が将来相続で揉めないようにと、心を込めて自筆で遺言書を作成されました。「自宅は一緒に住んで面倒を見てくれている長男Bに、預貯金は離れて暮らす次男Cに」という内容で、日付と名前を書き、印鑑も押したつもりでした。
しかし、Aさんが亡くなった後、いざ相続手続きを進めようとしたところ、遺言書の日付が「令和〇年〇月吉日」と特定されていなかったこと、押された印鑑が実印ではなく普段使っていた認印だったことなど、法律で定められた形式を満たしていないことが判明。良かれと思って書いた遺言書は、残念ながら法的に無効となってしまいました。
結局、遺産をどう分けるか兄弟で話し合う「遺産分割協議」が必要になりました。「母さんは家を俺に残すと言っていたはずだ!」と主張する長男Bさんと、「法律では平等なはずだ。預金だけでは不公平すぎる!」と納得できない次男Cさんの間で意見は真っ向から対立。Aさんの「息子たちが揉めないように」という切なる願いとは裏腹に、兄弟間の関係には深い溝ができてしまいました。
教訓
自筆証書遺言は、費用がかからず手軽に作成できる反面、法律で定められた厳格なルールを守らないと簡単に無効になってしまいます。ご自身の想いを確実に実現し、かえってトラブルを招かないためにも、専門家が関与する公正証書遺言の作成を強くおすすめします。
事例2:「介護したのだから多く欲しい」兄 vs 「法律通り平等に」弟 (遺言書と介護の貢献が絡むケース)
母が亡くなり、相続人は長男と次男の二人。母は生前に、「長男に8割、次男に2割。介護も頼むから」という内容の遺言書を自筆で作成し、長男にだけ伝えていました。実際に、長男は10年以上にわたり母の介護を一人で献身的に行っていました。
相続が始まり、長男は弟に遺言書の内容を伝え、「母さんの遺言もあるし、介護も俺がやったんだから、遺言通りとは言わないまでも、せめて6割はもらわないと割に合わない」と主張しました。しかし、弟は「母さんの遺言は知らなかったし、そもそも法定相続分は平等のはずだ。財産はきっちり半分に分けるべきだ」と反論。
遺言書の有効性も確認できず(※仮に有効でも、弟には最低限の取り分を主張できる「遺留分」という権利があります)、介護の貢献度(寄与分)についても、「同居していたんだから当たり前だ」「金銭的な援助も受けていただろ」など、兄弟間の言い分は全くかみ合いません。結局、「昔から兄さんばかり贔屓されていた」「お前だって親に迷惑ばかりかけていたじゃないか」と過去の不満まで持ち出し、収拾がつかない泥沼の争いに発展してしまいました…
教訓
介護の貢献と遺産の配分は、非常に感情が絡みやすくデリケートな問題です。生前に、介護の負担について家族全員でよく話し合い、その貢献にどのように報いるかを明確にし、法的に有効かつ遺留分にも配慮した遺言書(公正証書遺言推奨)で定めておくことが極めて重要です。「多く渡す」という曖昧な遺言や口約束だけでは、かえって深刻な争いを招く可能性があります。
事例3:見つからなければ… 破り捨てられた(かもしれない)遺言書
亡くなった父には、前妻との間に長男が一人、そして後妻である母との間に次男と三男がいました。父は公正証書遺言を作成し、「全財産を後妻(母)と、後妻との間の子である次男・三男に相続させる」と記していましたが、その遺言書の存在を前妻の子である長男には伝えていませんでした。
父の死後、遺品整理をしていた際に、長男が偶然、父の書斎から遺言書の謄本(写し)を見つけてしまいました。「自分には一円も財産が残されないのか…」と強いショックと疎外感を覚えた長男は、その遺言書を誰にも見せず、その場で黙って破り捨ててしまいました。
その後、遺言書の存在を知らない母や他の兄弟は、法定相続分に従って遺産分割協議を始めましたが、「長男がいるのに、なぜ後妻側で遺産を管理しようとするのか」といった疑念や対立が生まれ、相続は一向に進みませんでした。(※幸い、このケースでは公証役場に原本があったため、後日、遺言の存在が明らかになりましたが、もしこれが自筆証書遺言で、保管場所も不明だったら…と考えると恐ろしい事態です)。
教訓
自筆証書遺言には、紛失、隠匿、改ざんのリスクが常に付きまといます。公正証書遺言であれば、原本が公証役場に安全に保管されるため、このような心配はありません。 また、遺言書の存在や内容(少なくともその概要や想い)は、関係する相続人全員に、できれば生前に伝えておく方が、無用な疑念や隠蔽行為を防ぎ、円満な相続に繋がります。
注意ポイント:法務局保管制度も万全ではない
自筆証書遺言を法務局で保管する制度(自筆証書遺言保管制度)もありますが、注意が必要です。法務局はあくまで遺言書を「預かる」だけであり、その内容が法的に有効か、あるいは将来の家族関係を考慮して適切か、といった点までは一切チェックしてくれません。 その結果、無効な遺言書や、かえって家族間の不和を招くような遺言書が残されてしまうケースも少なくありません。確実性を求めるならば、やはり専門家が関与し内容までしっかり検討する公正証書遺言が最善の方法と言えます。
事例4:「自宅はもらったけど…」相続税が払えない!
母から長女へ、「お前がずっと住めるように、この家(評価額5,000万円)をあなたに相続させる」という内容の遺言書(公正証書)がありました。長女は母の想いに感謝し、家を相続しましたが、母の財産はほとんどがこの自宅不動産で、長女自身もまとまった預貯金を持っているわけではありませんでした。
その後、相続税の計算をしたところ、数百万円の納税が必要であることが判明。相続税は原則として亡くなってから10か月以内に現金で一括納付しなければなりません。納税資金をどうしても準備できなかった長女は、母から受け継いだばかりの、思い出がたくさん詰まった大切な自宅を、泣く泣く売却せざるを得なくなってしまいました…
教訓
遺言書で財産の分け方を決める際には、その結果として発生する相続税の負担についても必ず考慮することが重要です。特に不動産など、すぐに現金化できない財産を特定の相続人に集中させる場合は、その相続人が納税資金を準備できるか(預貯金は十分か、生命保険金を活用できないか等)を事前に確認し、場合によっては納税対策もセットで計画しておく必要があります。
事例5:「お世話になった姪に…」で相続税がまさかの2割増!?
お子さんのいらっしゃらないAさんは、姪のB子さんに、病気の時など本当によくお世話になったため、「私の財産は全て、感謝の気持ちを込めてB子に遺贈する」という公正証書遺言を作成しました。
Aさんが亡くなり、B子さんは感謝と共に遺産を受け継ぎましたが、相続税を計算する段階になって、納税額が通常よりも2割も高くなることを知って驚きました。相続税法では、亡くなった方の配偶者と一親等の血族(子供や親)以外の人が遺産を取得した場合、その人の相続税額が2割加算されるというルールがあるのです(相続税の2割加算)。Aさんがこの制度を知っていれば、生前贈与など、B子さんの負担が少なくなる別の方法も検討できたかもしれません。
教訓
誰に財産を渡すかによって、相続税の負担は大きく変わることがあります。特に、お孫さんや兄弟姉妹、甥姪、あるいは血縁関係のない方へ財産を遺したいと考えている場合は、「相続税の2割加算」に注意が必要です。遺言書を作成する際には、税金のことも含めて、事前に相続に詳しい専門家(税理士など)に相談することをおすすめします。
もし話し合いがまとまらないと…待っているのは更なる困難
これらの事例のように、遺産分割の話し合いがこじれ、まとまらない場合、最終的には家庭裁判所での調停や審判といった手続きに頼らざるを得なくなります。しかし、それは決して望ましい解決策ではありません。
裁判所の手続きは、解決までに数年単位の時間がかかることも珍しくなく、弁護士費用も高額になりがちです。それ以上に辛いのは、かつては仲の良かった家族や親戚と、お金を巡って争わなければならない精神的な苦痛です。一度ひびが入った関係は、たとえ法的な解決がついたとしても、元通りになることは難しいでしょう。
さらに、遺産分割協議が長引くと、相続税の申告・納税期限(死亡後10か月以内)に間に合わせるのが困難になります。分割が決まっていなくても、原則として法定相続分で相続したものとみなして申告・納税が必要になり、この際、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった有利な特例が適用できず、一時的に本来より多額の税金を納めなければならないリスクも生じます。
争いが長引けば長引くほど、時間も、お金も、そして何よりかけがえのない家族の絆も失われていくのです。故人の「家族仲良くいてほしい」という願いも、叶わぬものとなってしまいます。
\初回無料診断/
なぜ相続トラブルは起きてしまうのか?根本原因を探る
相続トラブルが起きる根本的な原因は、突き詰めると以下の点に集約されることが多いです。
- 「遺言書」の問題:遺言書がない、あっても無効、内容が不明確、想いが伝わらないなど。
- コミュニケーション不足:生前に家族間で相続について話し合う機会がない、あるいは避けている。
- 情報の非対称性:相続人の間で、財産の内容や故人の想いに関する情報共有ができていない。
- 権利意識の高まり:「法律で認められた自分の権利(相続分)はきっちり主張したい」と考える人が増えている。
- 感情的なしこり:過去の親子関係や兄弟姉妹間の関係性が、相続を機に噴出する。
特に、「法律で定められたルール(法定相続分)と、故人の想いや家族の実情(介護の貢献など)とのギャップ」が、争いを引き起こす大きな要因となります。このギャップを埋める最も有効な手段が、法的に有効で、かつ故人の想いが込められた「遺言書」なのです。
遺産相続トラブルを回避するための絶対条件:「有効な遺言書」の作成
遺産相続トラブルを未然に防ぐために、最も重要かつ効果的な対策は、ご本人が元気なうちに、法的に有効な「遺言書」を作成しておくことです。
遺言書があれば、原則としてその内容が法定相続分よりも優先されます。つまり、遺産分割協議を経ずに、故人の意思に沿った財産の分配が可能になるため、相続人間の争いを大幅に減らすことができます。
ただし、「自筆証書遺言」には要注意!
手軽に作成できる自筆証書遺言ですが、前述の通り、多くのリスクが伴います。
自筆証書遺言の主なリスク
- 無効になるリスク:日付、署名、押印など、形式要件を満たさず無効になる可能性が高い。
- 紛失・隠匿・改ざんのリスク:保管場所が不明になったり、悪意のある相続人に破棄されたりする恐れがある。
- 内容の不明確さによるリスク:表現が曖昧で解釈を巡って争いになる可能性がある。
- 検認手続きの手間:相続開始後、家庭裁判所での「検認」という手続きが必要(時間と手間がかかる)。
- 法務局保管制度の限界:2020年から法務局で保管できる制度が始まりましたが、これはあくまで「保管」してくれるだけで、遺言の内容が法的に有効か、あるいはその内容で将来揉めないか、といった点まではチェックしてくれません。結果として、不適切な内容の遺言書が残され、かえってトラブルの原因になることもあります。
エンディングノートやビデオレターなども、故人の想いを伝える手段としては有効ですが、法的な遺言としての効力はありません。財産の分け方について法的な拘束力を持たせるには、やはり正式な遺言書が必要です。
トラブル回避には「公正証書遺言」がベスト
そこで私たちが強く推奨するのが、「公正証書遺言」です。
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成に関与し、内容の法的な有効性を確認した上で、原本を公証役場に保管する方式です。
公正証書遺言のメリット
- 無効になるリスクが極めて低い:専門家が作成するため、形式不備の心配がない。
- 紛失・隠匿・改ざんの心配がない:原本が公証役場に保管されるため安全・確実。
- 検認手続きが不要:相続開始後、すぐに相続手続きを進められる。
- 内容の明確性:公証人が内容を確認し、明確な表現で作成できる。
- 意思能力の証明力:作成時に公証人が本人の意思能力を確認するため、後で争われにくい。
作成には費用(公証役場手数料や専門家報酬)がかかりますが、将来の相続トラブルを回避し、ご自身の意思を確実に実現するための「保険」と考えれば、決して高い費用ではありません。
あきた相続・贈与相談プラザでは、お客様のご意向を丁寧に伺い、相続税や遺留分にも配慮した最適な遺言内容をご提案し、公証役場とのやり取りも含めて公正証書遺言の作成を全面的にサポートいたします。
遺言書は「オープン」に!「気持ち」を伝える工夫も
遺言書を作成したら、その内容を秘密にするのではなく、ご家族にオープンに伝えることをお勧めします。どの財産を誰に、なぜそう分けたのか、生前にご自身の言葉で説明することで、相続人間の誤解や不信感を防ぐことができます。
また、遺言書には「付言事項」として、法的な効力はありませんが、ご家族への感謝の気持ちや、遺産分割の理由などを書き添えることができます。これも、円満な相続を実現するための有効な手段です。
相続トラブルが起きてしまったら… 時間もお金も、そして家族の絆も失う可能性
もし、遺産分割協議がまとまらず、家庭裁判所での調停や審判にまで発展してしまった場合、どうなるのでしょうか。
- 時間と費用の浪費:解決までに数年かかることも珍しくなく、弁護士費用も高額になります。
- 精神的な負担:家族間での争いは、精神的に非常に大きなストレスとなります。
- 家族関係の破綻:一度こじれた関係は、元に戻らないことがほとんどです。お金の問題以上に、かけがえのない家族の絆を失うことになります。
- 相続税申告への影響:遺産分割がまとまらないと、相続税の申告(10か月以内)において、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった有利な制度が使えず、一時的に多額の納税が必要になる場合があります。
「まさかうちが…」と思うかもしれませんが、相続トラブルは誰にでも起こりうる現実です。そして、一度起きてしまうと、失うものはあまりにも大きいのです。
相続トラブルを防ぐために、今できること
相続トラブルを未然に防ぎ、円満な相続を実現するためには、ご本人が元気なうちに、早めに対策を講じることが何よりも重要です。
- 有効な遺言書(公正証書遺言)を作成する。
- 遺言書の内容や相続についての想いを、家族に伝えておく。
- 相続財産の内容を把握し、整理しておく。
- 相続手続きや税金について、専門家に相談しておく。
特に、公正証書遺言の作成は、最も確実で効果的なトラブル予防策と言えます。
秋田市の相続トラブル相談は、あきた相続・贈与相談プラザへ
あきた相続・贈与相談プラザでは、相続に関する様々なお悩みやトラブルに対応するため、税理士だけでなく、司法書士とも緊密に連携しています。また、争いが深刻化し、法的な解決が必要な場合には、提携している経験豊富な弁護士をご紹介いたします。
私たちは、単に手続きを代行するだけでなく、お客様のご状況やご意向を丁寧にお伺いし、円満な相続を実現するためのお手伝いをさせていただきます。
- 「将来、子供たちが揉めないか心配…」
- 「有効な遺言書を作成しておきたい」
- 「相続手続きが大変そうなので、専門家に任せたい」
- 「すでに家族間で揉めそうな気配がある…」
このようなお悩みやご不安をお持ちでしたら、どうか一人で抱え込まず、私たちにご相談ください。
初回のご面談(約60分)は無料です。まずは、あなたの状況やお悩みについて、私たちにお話しをお聞かせください。秘密は厳守いたします。その上で、今後の最適な進め方や、私たちがご提供できるサポートについて、分かりやすくご説明させていただきます。
大切なご家族のために、そしてご自身の安心のために、今すぐ行動を起こしましょう。
\初回無料診断/