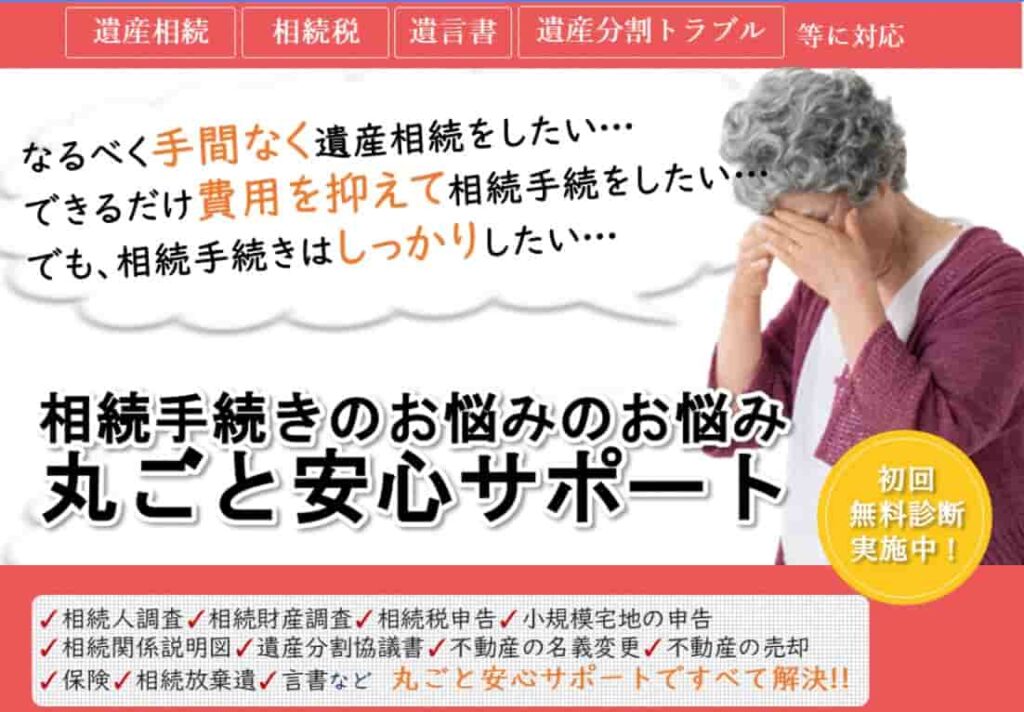お悔やみ申し上げます。大切な方を亡くされ、大変な時期かと存じます。加えて、相続に関する手続きは種類が多く、期限が定められているものもあり、何から手をつけて良いか分からず途方に暮れてしまうお気持ち、本当によく分かります。
遺産相続の手続きは、多くの方が人生で何度も経験するものではありません。そのため、慣れない作業に戸惑い、時間的にも精神的にも大きな負担を感じられる方が少なくありません。
この記事では、相続発生後に行うべき主な手続きの流れを、ステップごとに分かりやすく解説します。秋田市にお住まいの皆様が、少しでも安心して手続きを進められるよう、期限や必要書類、注意点なども具体的にお伝えしていきます。この記事を読むことで、相続手続きの全体像と、今やるべきことが明確になるはずです。
ここでは、「相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本」の著者であり、あきた相続・贈与相談プラザ(運営:秋田税理士事務所)の代表、税理士 坂根崇真が解説します。
相続手続きの主な流れ(概要)
- 【死亡直後~】死亡関連の手続き(死亡届・火葬許可など)
- 【死亡後すみやかに】公的手続き(年金・健康保険など)、各種契約の確認・停止
- 【死亡後すみやかに~3ヶ月以内】相続の基本情報の確認(遺言書・相続人・財産調査)
- 【死亡後3ヶ月以内】相続方法の決定(相続放棄・限定承認の検討)
- 【死亡後4ヶ月以内】所得税の申告(準確定申告 ※必要な場合)
- 【~10ヶ月以内】遺産の分け方を決定(遺産分割協議・協議書作成)
- 【遺産分割後すみやかに】財産の名義変更(預貯金・不動産・株式など)
- 【死亡後10ヶ月以内】相続税の申告・納税(※必要な場合)
※上記は一般的な流れであり、状況によって順番が前後したり、不要な手続きもあります。
このように、相続手続きは多岐にわたり、それぞれに期限が設けられています。ご自身ですべて行うのは想像以上に大変です。「手続きが複雑でよく分からない」「仕事や家事で時間が取れない」「他の相続人と連絡を取り合うのが難しい」…そんな時は、無理せず専門家にご相談ください。
あきた相続・贈与相談プラザでは、相続手続きを丸ごとサポートする「遺産整理業務(相続手続きおまかせパック)」もご用意しております。お客様の負担を最小限に抑え、円満かつスムーズな相続を実現するお手伝いをいたします。まずは無料面談で、あなたのお困りごとをお聞かせください。
\初回無料診断/
遺産相続手続き 詳細ステップ解説
それでは、相続発生後に行うべき手続きを、ステップごとに詳しく見ていきましょう。
【ステップ1:死亡直後の手続き】(期限:死亡を知った日から7日以内など)
ご家族が亡くなられた直後は、精神的にも大変な時期ですが、まず行わなければならない手続きがあります。
- 死亡診断書(死体検案書)の受け取り:病院で亡くなった場合は医師から「死亡診断書」が、それ以外(自宅での突然死など)の場合は警察の検案後に「死体検案書」が発行されます。これは後の手続きで必要になる重要な書類です。
- 死亡届の提出:死亡を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3ヶ月以内)に、死亡診断書(死体検案書)を添付して、市区町村役場(亡くなった方の死亡地・本籍地、または届出人の所在地)に提出します。秋田市の場合は、秋田市役所の市民課または各市民サービスセンター(支所)で手続きできます。通常は葬儀社が代行してくれることが多いです。
- 火葬(埋葬)許可証の受け取り:死亡届が受理されると、「火葬(埋葬)許可証」が交付されます。これがないと火葬・埋葬ができませんので、必ず受け取りましょう。
この段階の手続きは、葬儀社に依頼していれば、段取りを指示・代行してくれることがほとんどですので、まずは葬儀社とよく連携しましょう。
【ステップ2:公的手続き・各種契約の確認・停止】(期限:10日~14日以内など)
葬儀などが一段落したら、公的な手続きや各種契約に関する手続きを進めます。
- 年金受給停止の手続き:亡くなった方が年金を受給していた場合、厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内に年金事務所または市区町村役場に「年金受給者死亡届」を提出し、受給を停止します。
- 未支給年金の請求:亡くなった方が受け取っていない年金がある場合、生計を同一にしていた遺族が請求できます。
- 健康保険・介護保険の手続き:
- 国民健康保険・後期高齢者医療制度:資格喪失届を提出し、保険証を返却します(14日以内)。葬祭費が支給される場合がありますので確認しましょう。
- 勤務先の健康保険:勤務先を通じて資格喪失手続きを行います。埋葬料(費)が支給される場合があります。
- 介護保険:資格喪失届を提出し、保険証を返却します(14日以内)。
- 世帯主変更届:亡くなった方が世帯主で、残された世帯員が2人以上いる場合は、14日以内に市区町村役場に届け出が必要です。
- 公共料金等の名義変更・解約:電気、ガス、水道、電話、NHKなどの契約者名義の変更または解約手続きを行います。支払い方法が口座振替の場合は、口座凍結前に変更が必要です。
- 金融機関への連絡と口座凍結:亡くなった方の預金口座は、相続手続きが完了するまで、不正な引き出しを防ぐために金融機関に連絡して凍結してもらうのが一般的です。ただし、凍結されると公共料金などの引き落としもできなくなるため、事前に支払い方法を変更しておく必要があります。
- 生命保険金の請求:亡くなった方が生命保険に加入していた場合、保険会社に連絡し、保険金請求の手続きを行います。受取人固有の財産とされるため、遺産分割の対象外ですが、相続税の計算上は「みなし相続財産」として扱われる場合があります。
- その他:クレジットカード、各種会員サービス、運転免許証、パスポートなどの解約・返納手続きも必要に応じて行います。
これらの手続きは多岐にわたり、それぞれ窓口も異なります。漏れがないようにリストアップし、計画的に進めることが大切です。ご自身で対応が難しい場合は、あきた相続・贈与相談プラザの遺産整理業務をご検討ください。
【ステップ3:相続の基本情報の確認】(期限:3ヶ月以内を目安に)
今後の相続手続きの基礎となる情報を収集・確認します。特に相続放棄などを検討する場合、このステップは非常に重要です。
- 遺言書の有無の確認:
- 公正証書遺言の場合:最寄りの公証役場で、全国の公証役場に保管されている遺言書の有無を検索できます。
- 自筆証書遺言の場合:故人の自宅(金庫、仏壇、書斎など)や、貸金庫などを探します。法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用していた可能性もあるため、法務局にも確認します。
- 注意点:封印された自筆証書遺言(法務局保管以外)が見つかった場合、勝手に開封してはいけません。家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。勝手に開封すると過料(罰金のようなもの)を科される可能性があります。公正証書遺言や法務局で保管されていた自筆証書遺言は検認不要です。
- 遺言書があれば、原則としてその内容に従って遺産分割が進められます。遺言書がない場合は、次の「相続人調査」と「財産調査」の結果をもとに、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。
- 相続人の調査・確定:
- 誰が法的な相続人になるのかを確定させるため、亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)を取得します。これにより、前妻(夫)との間の子供や、認知した子供、養子などがいないかを確認します。
- 合わせて、相続人全員の現在の戸籍謄本も必要になります。
- 戸籍の収集は、本籍地が各地に点在している場合など、非常に手間がかかる作業です。あきた相続・贈与相談プラザでは、行政書士や司法書士の職権による戸籍収集代行も可能です。
- 相続財産・債務の調査:
- 亡くなった方がどのような財産(プラスの財産)と債務(マイナスの財産)を持っていたかを調査します。
- プラスの財産:預貯金通帳、不動産の権利証(登記識別情報通知書)、固定資産税の納税通知書、株式や投資信託の取引報告書、保険証券、車検証などを手掛かりに調査します。金融機関に残高証明書の発行を依頼したり、市区町村役場(秋田市なら資産税課など)で名寄帳(固定資産課税台帳)を取得したりします。
- マイナスの財産:借金の契約書、督促状、クレジットカードの利用明細などを確認します。信用情報機関に照会することも有効です。
- 財産調査は相続手続きの中でも特に重要で、漏れがあると後でトラブルになったり、相続税申告で問題になったりします。
この段階で、遺言書の有無、相続人の範囲、そして大まかな財産と債務の状況を把握することが、次のステップに進むための前提となります。
【ステップ4:相続方法の決定】(期限:死亡を知った日から3ヶ月以内)
ステップ3の調査の結果、明らかに借金の方が多い場合や、相続に関わりたくない特別な事情がある場合などは、相続の方法を選択する必要があります。この選択は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
- 単純承認:プラスの財産もマイナスの財産(借金)も全て引き継ぐ方法です。特別な手続きは不要で、3ヶ月以内に何もしなければ自動的に単純承認したとみなされます。
- 相続放棄:プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない方法です。借金が多い場合に有効ですが、不動産などプラスの財産も手放すことになります。一度放棄すると撤回はできません。
- 限定承認:引き継いだプラスの財産の範囲内でマイナスの財産(借金)を弁済し、もし財産が残ればそれを引き継ぐ方法です。借金の額が不明確な場合に有効ですが、手続きが非常に複雑で、相続人全員で申し立てる必要があります。
3ヶ月の期限は非常に短いため、借金の可能性がある場合は、すぐに専門家(弁護士や司法書士)に相談することをおすすめします。あきた相続・贈与相談プラザにご相談いただければ、提携している相続に強い弁護士や司法書士をご紹介いたします。期限を過ぎていても、事情によっては相続放棄が認められるケースもありますので、諦めずにご相談ください。
【ステップ5:所得税の申告(準確定申告)】(期限:死亡を知った日の翌日から4ヶ月以内)
亡くなった方が、その年の1月1日から亡くなった日までの間に一定以上の所得(給与所得以外に、事業所得や不動産所得、年金収入など)があった場合、相続人が代わりに所得税の確定申告を行う必要があります。これを「準確定申告」といいます。
対象となるのは、主に個人事業主や、不動産賃貸収入があった方、年間の給与収入が2,000万円を超えていた方、2か所以上から給与を得ていた方などです。申告が必要かどうか不明な場合は、まずはあきた相続・贈与相談プラザにお話しをお聞かせください。
準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。
(関連記事)
【相続税申告期限】いつまでに払う?10か月の超短い期限
【ステップ6:遺産の分け方を決定(遺産分割協議)】(期限:相続税申告期限の10ヶ月以内が目安)
遺言書がない場合、または遺言書で分け方が指定されていない財産がある場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。これを「遺産分割協議」といいます。
- 協議は相続人全員が参加して行う必要があり、一人でも欠けると無効になります。
- 全員が合意したら、その内容を明確にするために「遺産分割協議書」を作成します。この書類には、相続人全員が署名し、実印を押印します。遺産分割協議書は、後の預貯金の解約や不動産の名義変更手続きで必要になります。
- 協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになりますが、時間も費用もかかり、精神的な負担も大きいため、できる限り話し合いでの解決を目指したいところです。
- あきた相続・贈与相談プラザでは、遺産分割協議が円滑に進むようなアドバイスや、相続税額を考慮した有利な分割案のご提案、遺産分割協議書の作成サポートも行っています。万が一、協議がこじれてしまった場合には、提携弁護士をご紹介することも可能です。
遺産分割協議には明確な期限はありませんが、後述する相続税申告(10ヶ月以内)までに完了していることが望ましいです。
【ステップ7:財産の名義変更】(期限:特になし。ただし相続登記は義務化)
遺言書または遺産分割協議書の内容に従って、各財産の名義を相続人に変更する手続きを行います。
- 預貯金:金融機関ごとに所定の書類(戸籍謄本、遺言書または遺産分割協議書、印鑑証明書など)を提出し、解約または名義変更を行います。
- 不動産:法務局(秋田市なら秋田地方法務局)に「相続登記」を申請します。2024年4月1日から相続登記は義務化され、正当な理由なく怠ると過料が科される可能性があります。手続きには専門知識が必要なため、司法書士に依頼するのが一般的です。あきた相続・贈与相談プラザでは、提携司法書士が責任を持って対応いたします。
- 株式・投資信託:証券会社に連絡し、所定の手続きを行います。
- 自動車:運輸支局(秋田運輸支局など)で名義変更手続きを行います。
- その他:ゴルフ会員権なども名義変更が必要です。
これらの名義変更手続きも、必要書類が多く、各窓口での手続きが必要となるため、時間と手間がかかります。特に金融機関の手続きは、予約が必要な場合も多く、時間がかかる傾向にあります。
【ステップ8:相続税の申告・納税】(期限:死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内)
ステップ3で調査した財産の総額が、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、相続税の申告と納税が必要になる可能性があります。
- 申告要否の判断:財産の評価(特に不動産は複雑)、各種特例の適用などを考慮して、申告が必要かどうかを判断します。
- 申告・納税:申告が必要な場合は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する税務署(秋田市なら秋田南税務署または秋田北税務署)に相続税申告書を提出し、納税も済ませる必要があります。
- 注意点:相続税がかからない場合でも、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった有利な特例を使うためには、期限内に申告書を提出する必要がある点に注意が必要です。
相続税の計算と申告は非常に専門性が高く、税理士によって納税額が変わります。申告が必要な場合は、必ず相続専門の税理士に依頼しましょう。
(関連記事)
相続税はいくらまで無税?いくらからかかる?秋田市の税理士が解説
相続手続きは専門家への依頼が安心・確実です
ここまで見てきたように、遺産相続の手続きは、種類が多く、期限も厳しく、専門的な知識も必要とされます。働きながら、あるいはご自身の生活を送りながら、これら全ての手続きをご自身で行うのは、時間的にも精神的にも大変な負担です。
特に、
- 何から手をつけていいか分からない
- 手続きが多くて、自分だけではとてもできそうにない
- 仕事や家事が忙しくて時間が取れない
- 戸籍集めや財産調査が難航している
- 相続人の間で意見がまとまらず、揉めそうだ
- 相続税がかかるか心配、申告が必要かもしれない
- 不動産の名義変更(相続登記)をどうすればいいか分からない
といったお悩みをお持ちの方は、無理をせず、私たち相続の専門家にお任せいただくことを強くお勧めします。
あきた相続・贈与相談プラザでは、相続に関するあらゆる手続きを代行する「遺産整理業務(相続手続きおまかせパック)」をご提供しています。
あきた相続・贈与相談プラザの遺産整理業務(相続手続きおまかせパック)
面倒で複雑な相続手続きを、相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士連携)がお客様に代わって一括で代行するサービスです。
<サポート内容の例>
- 相続に関するお悩み相談
- 相続人の調査・確定(戸籍謄本等の収集代行)
- 相続財産の調査・評価、財産目録の作成
- 遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成支援
- 預貯金の解約・払い戻し、名義変更
- 不動産の相続登記(提携司法書士のご紹介※)
- 株式・投資信託等の名義変更
- 相続税申告の要否判断、申告書の作成・提出(必要な場合※)
- その他、各種手続きの代行
お客様に行っていただくのは、基本的に必要書類へのご署名・ご捺印(実印)と印鑑証明書の取得のみです。役所や金融機関、法務局などへの面倒な手続きは全て私たちが行います。
<料金>
遺産総額に応じた明朗な料金体系で、金融機関が提供する同様のサービスの半値以下と格安です。詳しくは料金ページをご覧ください。初回のご面談は無料ですので、まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。
※司法書士業務や税理士業務などは別報酬。
専門家に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
- 時間と手間が大幅に削減できる
- 正確かつ迅速に手続きが進められる
- 法的なリスクや手続き漏れを防げる
- 精神的な負担が軽減され、故人を偲ぶ時間に専念できる
- 相続人間の公平性が保たれ、トラブルを防止できる
- 相続税の節税に繋がる場合がある
まとめ:相続手続きは早めの相談が鍵
遺産相続の手続きは、想像以上に複雑で、多くの時間と労力を要します。そして、多くの手続きには期限があり、それを過ぎてしまうと不利益を被る可能性もあります。
大切なのは、一人で抱え込まず、できるだけ早い段階で専門家に相談することです。
あきた相続・贈与相談プラザでは、秋田市および周辺地域の皆様の相続手続きを、親身になってサポートいたします。税理士・司法書士・行政書士が連携し、対応できるのが私たちの強みです。
初回のご面談(約60分)は無料です。「何から始めればいいの?」「費用はどれくらいかかる?」「うちは相続税、大丈夫?」など、どんなことでも構いません。まずは、あなたのお困りごとやご不安な点を、私たちにお聞かせください。
専門家が丁寧にお話を伺い、今後の流れや必要な手続き、私たちがご提供できるサポート内容について、分かりやすくご説明いたします。もちろん、相談したからといって、必ず依頼しなければならないわけではありませんので、ご安心ください。
相続手続きの第一歩は、専門家への相談から始まります。下のボタンから、お気軽にお問い合わせください。
\初回無料診断/